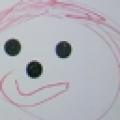
2024年4月の読書メーター 読んだ本の数:17冊 読んだページ数:3702ページ ナイス数:70ナイス ★先月に読んだ本一覧はこちら→ https://bookmeter.com/users/1118335/summary/monthly/2024/4
小学校の教員をしています。
小さな教室からのささやかな挑戦を続けています。
興味のあること(あくまでも興味であり、専門ではありません)は、国語、算数、特別支援教育、学級経営、アドラー心理学、『学び合い』、社会学です。
文学作品は、那須正幹、辻村深月、中村文則、又吉直樹、朝井リョウを読むことが多いです。
ここでは、自分の読書の記録として感想等を書き綴っていこう、と思っています。みなさんからのフィードバックがあれば嬉しいです。よろしくお願いします。
ブログでも書評等を書き綴っています。よければご覧ください。
「小さな教室からの挑戦」https://kyousituchallenge.hatenablog.jp/
この機能をご利用になるには会員登録(無料)のうえ、ログインする必要があります。
会員登録すると読んだ本の管理や、感想・レビューの投稿などが行なえます