柴野昌山(1982)「知識配分と組織的社会化ー「カリキュラムの社会学」を中心にー」(教育社会学研究第37集)
教育社会学で支配的な見方であった機能主義(学校は配分と社会化の機能を持っている)を批判する形で、「葛藤理論」(学校は身分集団間の闘争の場である)、そして、本稿で中心的に論じられている「新しい教育社会学」が表れた。これは、「学校において伝達される知識がどのように組織化され、カリキュラムに適応されるのか」、そのメカニズムを考察する立場である。この見方が誕生するに至った理由は①結果の不平等が露わになり、その原因が学校内における知識配分の不平等にあると考えられたこと②バーガーとルックマンの功績(知識社会学+現象学的アプローチ)にある。
「新しい教育社会学」は自明のものとされている教育的な現実を疑うことに特徴がある。現実は教師と生徒の相互作用ー「交渉」ーによって現出し、決して固定的に存在するものではない。そして、経験的な次元で示すために「カリキュラム」や「隠れたカリキュラム」にフォーカスを当てている。
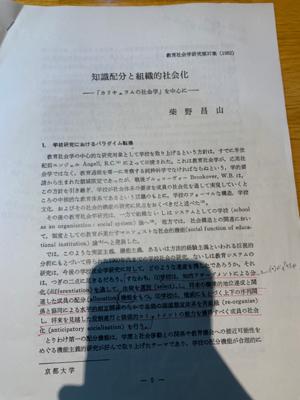
この機能をご利用になるには会員登録(無料)のうえ、ログインする必要があります。
会員登録すると読んだ本の管理や、感想・レビューの投稿などが行なえます