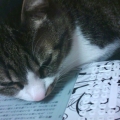
田畑を維持できなくなった家では、農地として貸すか分譲住宅にするか太陽光発電にするかしか選択肢が無い。売るには農地法の縛りがあり、農地転用すれば必ず造成して住宅か設備を構築しなければならない。農業はできなくとも、せめて雑木林として緑地で置いておくことができればよいが、個人では雑種地の課税に耐えられる家は多くない。またできれば水田のほうが保水・遊水機能が高いが、今の農政は水田から畑への転換を奨めている。空き家問題だけでなく、これらの問題をも含めて法制を変えていかないと、ますます暮らしにくい地になると憂える。
九尾の猫〔新訳版〕 (ハヤカワ・ミステリ文庫) >> あまりに面白すぎて、日本酒を呑み過ぎてしまった! https://bookmeter.com/books/9803004
中野信子の解釈によると、日本は耕作面積が少なく、災害が多く、資源が少ない、潜在的には貧しい国である。私も、決して他国がこぞって攻めて来るような国土ではないと思うのでこの点は納得である。さらにそこから、長い間貧しい国であったからこそ、生き延びるために「家族」という単位を重要視してきた、それが現代日本の頑強なイエ信仰の基ではないかと語っている。日本人はここから加速度的に減っていく。多くが結婚制度を選ばくなる。人間が協力し合う習性を持つ故に繁栄するなら、遠からず家族に代わる単位の概念が生まれるのだろう。
訳者あとがきに知った背景は覚えておきたい。チャペックはチェコ人である。この文章が連載された頃、ナチスドイツによる弾圧は既にチェコに及んでいた。兄ヨゼフは逮捕され、強制収容所で亡くなった。カレルはその直前に家で亡くなり、ナチの手を逃れている。そのような時世に、この平和で、笑いに満ちて、何気ない暮らしへの愛溢れる文章が書かれたのだ。それはチャペック兄弟が何を大切に思っていたかを、如実に表していると思った。そしたらその瞬間、とても深い思いが隠されたエッセイだったのだと悟って目が潤んでしまった。
人間がいる/いない、獣がいる/いないで村の自然の在りようが違ってくるあたりの観察が興味深い。獣に野菜や果樹の苗や芽を喰われては、労力と金と時間の喪失にがっかりしている。春は限られた回数しかその人に巡ってこない事実を想う。狩猟のときには決して言わなかった『鹿が憎い』にドキリとする。雌鹿を独りで仕留めた、愛すべきナツ(フィクションです)。面倒くさいと口では言いながら、服部文祥は溺愛していると感じる。久保俊治氏の猟犬フチを思い出した。女神だ。ナツの性別は知らんけど。
まあ、未成年には劇薬ですよね。吸収するとなったときの吸収っぷりが大人とは桁違いになる。相変わらず面倒くさいことを言っているけれど、読みたければ小難しい文章だって読む子供は読むのだから。…って言ってたのも服部文祥だったか。
「その土地に合うか合わないかは植えてみるしかない」めっちゃわかります!敷地外から好い感じに見えるように~なんて下心満載で植栽した多年草がしばらくすると群生として移動していることが・・。「すまん、そっちが良かったんか~」と詫びるしかないですが、ちょっとトホホです。ドクダミは地下でガンガン増えるのが欠点ですがエリアいっぱいに咲かせると思ったより可愛らしくて私は嫌いではないです(*´▽`*)そろそろお庭仕事の準備ですよね~♪
うわあいいなあ、多年草の大移動見てみたい! なんだか意思を感じそうです。球根ものが土に合わないといつの間にかまるごと消えるっていうのも他で聞いたことがあって、これまた、人間はお世話させていただくだけみたいな、小さいけれど壮大な世界。憧れますー。
私の住む町は、大きな川は無いが山に囲まれた地形で、ため池と水路がたくさんある。10年ほど前の台風時に浸水被害があった後、水路の改造工事をし、また最大限の被害を想定したハザードマップが作成された。しかしその後、ものすごい勢いで田畑が造成・住宅化されている。売れるうちに売れ、と暗黙の号令がかかっているかのようだ。特に店や学校が集まった人気のエリアは、そもそも土地が低い。急激に雨が降った際の保水・遊水機能を持つ水田がほとんどなくなった今、豪雨への耐性は低いだろうと知り合いの不動産屋と話したところだ。
田畑を維持できなくなった家では、農地として貸すか分譲住宅にするか太陽光発電にするかしか選択肢が無い。売るには農地法の縛りがあり、農地転用すれば必ず造成して住宅か設備を構築しなければならない。農業はできなくとも、せめて雑木林として緑地で置いておくことができればよいが、個人では雑種地の課税に耐えられる家は多くない。またできれば水田のほうが保水・遊水機能が高いが、今の農政は水田から畑への転換を奨めている。空き家問題だけでなく、これらの問題をも含めて法制を変えていかないと、ますます暮らしにくい地になると憂える。
この緻密な検討を記した本とたまたまの併読で佐野洋子のエッセイを読んでいる。末期がんの頃の洋子さんである。あまりの落差にボリボリと頭を掻きたくなる。ナッジ=望ましい決断≒合理的な決断を促すことと、個人的価値判断の程よいラインは人によって違う。医療行為をどのレベルで自分の身体に受け入れるかは患者の感覚で決めるべきなどと思っている私を担当するお医者には、今から思っても同情する。事故と思っていただきたい。
本は買って読む派。
本棚とKindleの両方で積読しています。
<ジャンルの配分目標>
フィクション(小説)45%
ノンフィクション(エッセイ)10%
ノンフィクション(ルポ、学術、趣味実用)45%
環境、自然、動物、人間、武術に関心があるみたいです。
歳を重ねるごと興味が広がり、読みたい本が増える加速度との板挟みです。できるだけ偏らないように、1冊読み終えたら違う種類の本を選ぶようにしています。
その結果、一見しっちゃかめっちゃかな選本ですが、大切にしたい核はしっかり一貫していることに、自信を覚えはじめています。
お気に入りは関心の似た方、感想に尊敬の感を持った方にしています。お義理では返しません。読み友さんの感想やつぶやきを読むのは楽しみですが、本に関係ないつぶやきが余りに多い方には、そっとさよならします。
<好きな作家リスト>
◆国内◆ 内澤旬子 内田樹 小野不由美 開高健 小松左京 佐野洋子 高野秀行 田口ランディ 種田山頭火 恒川光太郎 寺田寅彦 中島敦 中島らも 南木佳士 半藤一利 福岡伸一 森下典子 養老孟司
◆国外◆ アゴタ・クリストフ イーユン・リー オリヴァー・サックス ケン・リュウ サキ サマセット・モーム ジュンパ・ラヒリ ショーン・タン スティーヴン・キング マイケル・クライトン メイ・サートン (50音順)
<好きな出版社リスト>
亜紀書房 英治出版 光文社(古典新訳文庫) 草思社 築地書館 早川書房 ポプラ社(百年文庫) みすず書房 (50音順)
この機能をご利用になるには会員登録(無料)のうえ、ログインする必要があります。
会員登録すると読んだ本の管理や、感想・レビューの投稿などが行なえます
私の住む町は、大きな川は無いが山に囲まれた地形で、ため池と水路がたくさんある。10年ほど前の台風時に浸水被害があった後、水路の改造工事をし、また最大限の被害を想定したハザードマップが作成された。しかしその後、ものすごい勢いで田畑が造成・住宅化されている。売れるうちに売れ、と暗黙の号令がかかっているかのようだ。特に店や学校が集まった人気のエリアは、そもそも土地が低い。急激に雨が降った際の保水・遊水機能を持つ水田がほとんどなくなった今、豪雨への耐性は低いだろうと知り合いの不動産屋と話したところだ。