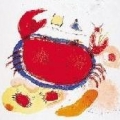
レアルさん、角倉了以の足跡を辿ったと言うことは、高瀬川沿いも歩かれたのでしょうか。角倉は地元富士川の河口にも碑が建っています。こちらは幕府から命じられた工事でしたがね。 川活動ですが、自然のことに留まらず、文化的な面にも関心があることは、広い視野で川を見ることが出来きますね。私が川の保全活動に参加していた時は、自然と環境が中心でした。元々自然や生物は好きでしたが、新たに環境と言う目で川を考えることが出来て、見方を広めてもらったと思います。
子どもの頃に『高瀬舟』の舞台となる高瀬川沿いを、また数年前には歴史仲間と「方広寺大仏再建」という歴史探訪で歩きました。子ども頃は小説の舞台、そして歴史好きなので大仏再建の舞台として、また川活動としては河川事業として、今はそれに加えて防災の視点として!仰るように1つのものを様々な視点からとらえる事によって見えてくるものがありますよね。
こんばんは。C.V.オールズバーグの中でも好きな作品です。この絵本を最初に読み彼の作品を色々読むようになりました。この絵本は、今の時期になると読みたくなる作品です。絵本の映画化はあまり好きではないのですが、この作品に関してはお勧めです。『ナイアガラの女王』は実話に基づいた作品。驚きました。良かったら手に取ってみてくださいね。
映画の邦題《ポーラー・エクスプレス》は、原題《The Poler Express》に合わせたんですね。 敢えて絵本のタイトル《 急行「北極号」》と変えたのは、理由があるのでしょう。 それから《ナイアガラの女王》は実話ですか。面白そう。読んでみます。
2018年から利用しています。
初めは気になった方のレビューを読むだけで十分だったのですが、そのうちに感想を書きたくなった。それが5年ほど前です。
【読書ジャンルについて】
若い時は、歴史とミステリー小説が中心。
歳と共に歴史好きは純然な方向に向かい、一方ミステリーは長い間離れていましたが、最近になってポツリポツリと読み始めました。
昔から地理や地図が好きだったので、次第に風土や紀行に関心が及ぶようになりました。
純文学は苦手だったのですが、最近急に覚醒しました。特に文豪作品は文豪の生き方、時代背景や社会に強い関心があります。
また、若い時は全く興味が無かった《古典・詩歌・絵本》の面白さに、最近目覚めてしまいました。
【好きな作家】
特別な存在なのが、司馬遼太郎。氏の考えが一つの指標でもあります。
歴史:池波正太郎、井沢元彦、塩野七生、陳舜臣、永井路子、半藤一利、藤沢周平、山岡荘八、吉川英治
ミステリー:内田康夫、大沢在昌、京極夏彦、島田荘司、R.チャンドラー、A.クリスティー、C.デクスター、A.C.ドイル、E.クイーン
その他:浅田次郎、阿刀田高、五木寛之、井上ひさし、井上靖、梅原猛、大岡信、高橋克彦、筒井康隆、松本清張、丸谷才一、宮沢賢治、村上春樹
読書メーター利用後には、赤羽末吉、芥川龍之介、安野光雅、小川洋子、川端康成、堀内誠一、アンデルセン、グリム兄弟なども読んでいます。…ただ現代人気作家や若手作家はあまり読んでないので、これから果敢に攻めたいと思っています。
(2025/1/4)
この機能をご利用になるには会員登録(無料)のうえ、ログインする必要があります。
会員登録すると読んだ本の管理や、感想・レビューの投稿などが行なえます